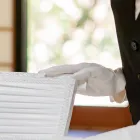葬儀に関する一般的な疑問に回答
Q&A
葬儀に関する一般的な疑問から、より具体的なご質問に至るまで、幅広い内容に対してわかりやすい回答を提供しています。家族葬の準備や進行、費用、法的な手続き、遺品整理など、葬儀に関連するさまざまな側面についての疑問を解消するためのリソースとして設計されています。専門知識を持つスタッフが丁寧にお答えし、葬儀のプロセスをスムーズに進めるお手伝いをします。
葬儀全般
- お寺さんを呼ばずに、無宗教ですれば安くはなりませんか?
- いいえ、お葬儀だけお寺さんを呼ばずに執り行ない、その後のお祭りはお寺さんに頼む。それでは、本来の主旨から外れ、故人もうかばれないでしょう。お寺さんにも失礼です。仏教徒である以上、お寺さんへ頼む事はさけられないでしょう。
- お寺さんと上手に付き合うにはどうすればよいでしょうか?
- 普段から、マメにお寺さんへ出向き住職と話をし、信頼関係を築く事が大事でしょう。些細な話や家族の事、先祖に手を合わせるなど、少しの心掛けでお寺さんと仲良くなる事が信頼関係を築く、一番の近道かも知れません。
困った時は、まず住職に相談する事により、優良な葬儀店をご紹介して頂いたり、お布施などの、お話にも気さくに相談にのって頂けるでしょう。
- 告別式の弔辞を依頼されましたが心得や書き方について教えて下さい。
- 弔辞を依頼されたら、何名の弔辞があるかを確認し、2~3名の時内容が重複しないように注意し、巻紙か奉書に黒か薄墨で丁寧に清書します。薄く書くのは「追悼の辞」「お別れのことば」と書きます。弔辞は、故人の生前の業績や人柄などをたたえ、その死を惜しむ気持ちを述べるものです。
具体的な文例は当社に弔辞集がありますので差し上げます。
- 神式でも焼香をするのですか?
- 神式では仏式のように焼香はしませんが玉串奉奠をします。焼香の替わりに榊の小枝を、胸の高さに捧げて枝先を霊前に向け、玉串台へ上げてから二礼二拍手 (弔事の場合は音をたてない) の後一礼して祭壇に向かったまま、2、3歩下がって体の向きを改め神職、遺族に一礼して退室します。
※天理教及び金光教は四拍手です。
- 焼香の作法を教えて下さい。
- 焼香は、「回し焼香」と「出焼香」の二通りの仕方があります。
(1) 回し焼香は、焼香器が回ってきましたら姿勢を正して頭礼 (かるく頭を下げる、合掌礼はしない) 続いて抹香をつまみ (回数は宗派により1~3回) 焚きます。終わって念珠を正しくかけ合掌礼 (念仏は自分の耳に聞こえる程度) し、次の人に焼香器を渡します。
(2) 出焼香 (呼出し焼香) の場合は、まず導師に合掌礼して焼香の前に進み姿勢を正しく頭礼し、続いて焼香し念珠を正しくかけ合掌、向きを変え導師に一礼して席へ戻ります。
地域や宗派によって異なります。本当に大事なのは心を込めて焼香をしてあげるのが、一番でしょう。
- 戒名 (法名) には、どんな種類があるのですか?
- 戒名は真宗では法名 (院釈、釈) 、日蓮宗では法号 (妙法) 、その他は戒名と呼ばれています。
戒名は男性 (院殿居士、院居士、居士、信市) 、女性 (院殿大姉、院大姉、大姉、信女) 、子供 (童子、童女、孩子<がいじ>、孩女) 。
院殿号は昔なら天皇、皇居、大名やその夫人に限られていました。現代では寺の興隆に貢献した人、または社会に尽くした人に与えられます。
- 戒名の費用はどのようになっているのでしょうか?
- 「信士」「居士」「院号」の順に費用が高くなりますが、戒名料の金額については寺院や地域によりかなり幅があるのが実情です。
支払いの方法もお経料と戒名料が別途になる場合もありますし、お経料に戒名料が含まれる場合もあります。
- お葬式に掛ける費用を、事前に知ることはできますか?
- 喪主と故人の年齢、職業、役職と、参列者の数、お葬式の会場が分かれば、何時でもお見積もりさせて頂きますので、お気軽にお申し付け下さい。
- お葬式に必要なお経の費用については、どれ位の金額でしょうか?
- お葬式の場で必要なお経料は、宗旨宗派や寺院等によって変わりますので、機会をみて率直に僧侶にお尋ねしてみましょう。
- お寺のお葬式の費用をお尋ねする事は失礼にあたるのでしょうか?
- お葬式についての習わしは一般人には分からないのが普通ですし、金額面で失礼があってはいけませんので遠慮なくお聞きしてよいでしょう。
なお「志で結構です」と言われた場合には、習わしを知っている方に教えていただくか、弊社にお尋ね下さい。標準的な金額の目安をお知らせ致します。
家族葬
- 家族だけで、葬儀を執り行う事は出来ますか?
- はい。近親者のみで、執り行う事は可能ですが、会社勤め、趣味の会等、交友関係の広い方などは、難しいといえるでしょう。
また、社会的地位、立場のある方の場合も、外部を完全にシャットアウトするのは難しいでしょう。
- 自宅で、誰にも知られないで家族葬を執り行なう事は出来ますか?
- いいえ。たしかに、会場費などの事を考えると低料金では執り行なえますが、自宅・地元の集会所・自治会館を利用した場合、ご近所様との付き合いを皆無にする事は、出来ないでしょう。
- では、完全に家族だけで葬儀を執り行なうには、どうすればよいのでしょうか?
- はい、西神戸ルミナリーホールと、ほんとうに無駄を省いた家族葬パックなどの併用により、より低価格・納得のいく故人様だけのお葬儀が執り行なえるのではと、考えております。
さも、必要かの様な説明をし、不必要な物を提供され最終的に高額の葬儀費用を支払わせられたというのは、よく聞く話です。我々は、そんな利益追求型の葬儀社では無く、ご家族と同じ目線に立ち親身になってお話をさせて頂く事こそが、これからの時代に求められている事ではないでしょうか。
西神戸ルミナリーホールの場合、最終合計金額を見てもらえれば一目瞭然です。
- 家族葬でお葬儀は、出来ますか?
- はい、執り行えます。
そもそも家族葬とは、いったい何なのでしょう?
近しい家族だけで、故人を偲んで送ってあげるのが、本来の姿ではないでしょうか。会社関係・ご近所・友人にも声をかけずに、家族が故人と過ごす最後の時間になります。
義理や一切のしがらみの無いお葬式です。本当に故人の事だけを想い、家族みんなが納得の行く形で送ってあげるのが家族葬だと思います。これは強制ではありません。
最近良く耳にするのが、家族葬でお葬式をしたいのですが、いくらで出来ますか?と言う質問です。一昔前に、密葬と言う言葉が流行ったように、言葉だけが先走りする事なく、本当に心のこもったお葬式を希望し執り行いたいものです。
- 家族葬で葬儀を執り行う場合、お布施も安くなるのですか?
- 最近、よく家族葬でお願いしますと耳にしますが、その中で規模も人数も少ないのだから、僧侶へのお布施も安くてもいいのですかと聞かれた事がありました。
いえいえ、おがんで頂くお経は規模に関わらず同じですから、
家族葬だから安いという事は無いと思いますよと、ご返答させて頂きました。
しかしながら、喪家様のお家の事情によりお布施の用意が困難なら一度ご住職様に相談してみては如何でしょうかと、アドバイスをさせて頂きました。
昔の方と最近の方では、宗教離れも進み意味合いや感覚が違うのもまた事実なのかも知れません。
- 家族葬で執り行う予定ですが、もし一般参列者が来た場合はどうすればいいのでしょうか?
- 万が一、会社関係の代表者やご近所さんが数名お見えになった場合は、再度家族葬での施行の趣旨を伝え、後日改めて丁寧にお礼をして頂くのが、最善ではないでしょうか。
最初のお話の段階で、家族のみで執り行うのか近しい方を数名招くのかを家族で相談し、担当者に相談すると供養品や振る舞う料理などのアドバイスをしてもらえるかもしれません。
小さな会場を借りて、予定に無い一般会葬者が多数お見えになれば、入って頂く事さえも困難になり大変失礼に当たりますので、呼ぶか呼ばないか、来る可能性があるのか無いのかを事前しっかりと相談して決定し家族みんなに伝える事により、こういったトラブルは避けられるでしょう。
最後に呼ばない時のアドバイスを一つ
日程は会社や学校を休まないといけないのではっきりと伝えますが、時間や執り行う葬儀会場の場所や施設の名称は伏せておく。
こうすることにより思わぬ事態は回避出来るでしょう。本当に近しい方やお世話になった方なら後日ご自宅にお線香をあげに来られる場合はありますが。
- 家族葬で執り行い、お寺さんは、呼ばない予定ですが、その場合位牌は、どうなるのですか?
- 戒名は、お寺さんに授けてもらい、お位牌に書いてもらうので、お寺さんを呼ばれない場合は、お位牌・戒名・初七日・逮夜表 (日程表) などは、ありません。
納骨やお盆や一周忌など節目のお経も頼みにくくなるので、葬儀の時には、良く相談の上、執り行うのが良いでしょう。
- 家族葬で、お葬式を頼んだ時、費用が高い安いがあるのは、何故ですか?
- 喪家の事情によって、火葬場の都合により、日延べによるドライアイスの追加や、自家用車の有る無しによって、ハイヤーやマイクロバスの発注であったり、身内同士でのお香典のやりとりの為、返礼品・料理などにより金額が、変わるものだと思われます。
祭壇が同じ値段なら、付随する物が多い少ないによって、変わる物だと思われます。
施行費用が高いと感じるのであれば、もう少し出費は掛かりますが、普通のお葬式をして、一般会葬者を呼ぶと、お香典が有りますので葬儀代の足しにする事は、出来るでしょう。
逆に、一切割切って、誰も呼ばずに家族だけで執り行うと、より出費は、抑えられると思います。
やはり一番大切なのは、心を込めて送り出してあげる気持ちなのですから、あまり金額に振り回させれない様に、バランスよく考えてみるのも、一つの方法でしょう。
- 家族葬のカタログを見て、内容的にも金額的にも、良かったので、家の近所の集会所で同じ内容の家族葬は、やって頂けますか?
- 西神戸ルミナリーホールの家族葬プランは、当会館での施行をモットーとし、セット価格にする事によって、より低価格にさせて頂いております。
会館以外での施行となりますと、別途設営費を申し受ける事となっておりますので、悪しからず、ご了解下さいませ。
- 家族葬は、どの会社も安価な値段が多い様に感じますが、私は母をお花で飾ってあげたいと思うのですが、そういった事は出来るのですか?
- 最近、花祭壇の需要も高まり、従来の祭壇にお花代を追加して頂けたら、小さな花祭壇もご用意しております。
白木の祭壇よりも、女性らしく、又華やかにお飾りし、お式を執り行う事が、可能です。
その他
- 会員じゃないと会館を使えないですか?
- 会員様以外でも会館をご使用可能です。
会員様には会員特典がございますので登録をお勧めいたします。
登録料・年会費無料です。
- 年々、お布施が高くなっている様な気がするのですが?
- はい。それは葬儀費用と同じで、物価の上昇や物の値打ちが上がっている為、その時、その時代に合わせた金額になっていると言えるでしょう。
昨今、お寺様との付き合いも薄くなりお葬儀・法事等の時にしか、接する事がなくなったのでお葬儀の時に2日で数万円と言われれば、高いと感じる方もおられるかと思いますが、先祖代々からのお付き合いで、日頃お寺へ出向く事もない訳ですから、何十年に一度と考えれば、そんなに高くは感じないのではないでしょうか。
田舎の方へ行けば、まだまだお寺様との付き合いは濃く、日頃からお寺の行事に参加し、お布施をしているので、お葬儀の時はあまり高額ではないのかもしれません。
その土地の習慣に、従うのがよいでしょう。
- 神葬祭の時、神官さんにお礼を包みたいのですが、表書きをどの様に書いたらよろしいでしょうか?
- 一般的には、「御礼」として表書きしています。
同じ神事でも地鎮祭、落成式のような祝事の時は、「祝詞料」としたり「御神酒料」「初穂料」とする事もあります。
弔事の時は、御礼と表書きしても間違いとは言えませんが、「御祭祀」となされば宜しいかと思います。
- よく「忌中」とか「喪中」とかいいますが、どう違うのでしょうか?
- 「忌中」とは、近親者が死亡した場合、死者の汚れをつけている期間であり、不吉なこと等を避けるため慎んでいる期間であり、時に死後49日間をいいます。
「喪中」とは、死後ある一定期間、家に閉じこもり、祝事や交際を差し控えている間のことをいいます。年賀状は一年欠礼しているのが現状です。
- 菩提寺について教えて下さい。
- 「菩提を弔う」という言葉がありますが、これは死者の冥福を祈るという意味です。ですから、菩提寺といえば自家がその信徒として所属し、祖先の菩提を弔う為のお寺のことで菩提寺檀那寺とも言います。
- なぜ焼香するのですか?
- 香をたくというのは俗人である。私達のけがれをとりはらって清浄になり心を正して仏に接するためであります。また、線香も同じ意味です。
- なぜ数珠を持つのですか?
- 数珠、誦珠、呪珠などと書きます。
数珠の数は108個であり、これは108の煩悩 (ぼんのう) を絶つという願いからです。その108個を基本とし、半分の54個、4分の1の27個のものがあります。
また、数珠の光徳は、仏と私達衆生の間に立って仏道修行を助けてくれる法具であるといえます。
- お通夜に出かける場合は、どうすればよいですか?
- 用意があれば礼服で、開式時間に合わせて出かけます。お参りを済ませた後もしばらく遺族の方と過ごすのが普通です。
また、通夜振る舞いを勧められたら断らないのがマナーです。但し、お酒はほどほどにし、車などの時はお酒は辞退します。
最近は勤務の関係でお葬式に出かけられない場合、お通夜に出かける事が多くなって参りました。
- お通夜にはどのような心構えが必要ですか?
- 会話が途切れがちになったり、お互いが黙ったまま「まるでお通夜のように」過ごしたりするのは、遺族を励まし、故人を慰め冥福を祈る本来の通夜の目的に適さないでしょう。
故人の楽しかった話、明るいニュース、下品にならないバカ話など適当な話題を選んで、座を盛り上げて明るい暖かみのある通夜の宴にしたいものですが、しめやかさを忘れてはならないでしょう。
- 香典の表書きは、どのように書けばよいですか?
- 香典の表書きは水引を境にして上に仏式なら「御香典」「御仏前」「御香料」。神式なら「御玉串料」「御神饌料」「御榊料」、キリスト教なら「御花料」「御弔慰」などとします。
そして下部の中央よりやや左よりに姓と名を書きます。右肩に小さく住所を書き添えるのが遺族に対して親切です。
また、香典包みの裏に金額を書いておくのが常識です。